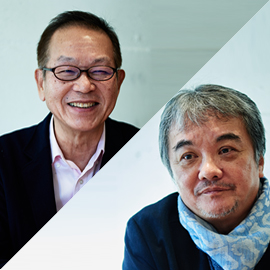目次
国民的ロングセラー「ガリガリ君」の開発者であり、育ての親である鈴木政次氏。1人あたりの売上高で1億円を超える脅威の生産性を誇る赤城乳業で、「ガリガリ君」だけでなく、「ガツンとみかん」、「ワッフルコーン(大手コンビニPB)」など、数々のヒット商品を生み出した伝説の商品開発部長でもあります。
菅賢治氏は、「恋のから騒ぎ」「踊る!さんま御殿!!」など数多くの人気バラエティ番組を手がけてきた元日本テレビの名物プロデューサー。「ダウンタウンのガキの使いやあらへんで!!」や「紅白」の裏番組で高視聴率を記録した「笑ってはいけない」シリーズでは時折番組にも出演し、“ガースー”という名前で親しまれていました。日本テレビを退社した今も、フリーのテレビプロデューサーとして活躍されています。
稀代のヒットメーカー2人が語る、ヒットを生み出す思考・企画発想の極意とは。初対面でしたが、意外なところでつながっていた二人、対談は大いに盛り上がりました。
タイトルも企画も、会議室で出たことなんてない


菅:
ダウンタウンの「笑ってはいけない」シリーズで、出演者を笑わせるための仕掛けのひとつとして、「ガリガリ君」ソーダに似たパッケージで「スガリスガリ君」ソーダというのを作ってもらったことがありまして(笑)。もちろん当時のものは、溶けてしまっていますが、先日、赤城乳業さんに講演に呼んでいただいて、そのときの話をしたら、わざわざパッケージを作って送ってくださって。僕の宝物なんですよ。ありがとうございます。
鈴木:
私のほうこそお礼を言わないといけなくて。著書『スーさんの「ガリガリ君」ヒット術』のタイトルは、菅さんがつけてくださったとお聞きしまして。本当にありがとうございました。
菅:
いえいえ、こちらこそ僭越の極みでした。出版社の社長が知り合いで、「スガちゃん、ちょっと考えてよ」と言われたので、参考になるかな、と出させてもらって。
鈴木:
びっくりしたのは、「スーさん」という名前を使ってもらえたことです。私は社内では仕事に厳しいですから「鬼の鈴木」と呼ばれていましたが、社外に向けては「スーさんと呼んでください」と申し上げていたんです(笑)。ですから、このタイトルはとてもうれしかった。
菅:
本の中身を読ませていただいたら、「スーさん」という感じがしたんです。親しみやすさを出したくて。実は何十個も考えたんですけどね(笑)。
鈴木:
ご縁に本当に感謝します。
菅:
鈴木さんは大ヒットを出されていて、気になる存在でした。「ガツンとみかん」も食べていまして、この「ガツン」もいいなぁ、と。「ガリガリ君」はもちろんですが、ネーミングがすばらしい。商品はネーミングが大事ですから。僕は番組タイトルにはそんなにこだわりは持っていないんです。10人いたら10人意見が違いますから、最後は一人で決めていました。合議制では決まらないんですよね。やっぱり誰かが責任を背負わないといけない。でも、商品の場合はネーミングがイメージを作りますから、その責任は重大です。
鈴木: 「ガリガリ君」のネーミングは、最終的には当時の専務井上秀樹(現会長)がつけたんです。もともとカップの「赤城しぐれ」を片手で食べられるようにする、というのが開発テーマでした。1981年、当時はモノが売れない厳しい時代でした。単にカップをワンハンドにしたら、安売りを求められると思いました。それで、フレーバーを変えることにしたんです。最初は何をやっていいのか、わかりませんでしたが、ハッと思ったのは、自分の業界ばかり見ていたらダメだ、ということでした。それで飲料の世界を見てみると、ロングセラーがあったわけです。それが、ラムネであり、ソーダでした。他の業界に救われたんですよ。でも当時、一緒に出したのが、グレープフルーツ味でした。これと差別化するために、青い色をつけたんですね。今はソーダの青色はスタンダードになっていますが、実はガリガリ君が始まりだったんですよ。そして、しぐれをスプーンでかくとき、ガリガリと音がしますから、これがネーミングになった。ただ、私にはひとつ過去に苦い思い出があって、一般名称のネーミングを他社に真似られたことがあったんです。「ガリガリ」だけだと固有名詞にならない。商標登録ができないわけですね。そうしたら専務が、「じゃあ、”君”をつければいいんじゃないか」と。これが面白い、ということで後に口コミでも広がっていったんです。
「ガリガリ君」のネーミングは、最終的には当時の専務井上秀樹(現会長)がつけたんです。もともとカップの「赤城しぐれ」を片手で食べられるようにする、というのが開発テーマでした。1981年、当時はモノが売れない厳しい時代でした。単にカップをワンハンドにしたら、安売りを求められると思いました。それで、フレーバーを変えることにしたんです。最初は何をやっていいのか、わかりませんでしたが、ハッと思ったのは、自分の業界ばかり見ていたらダメだ、ということでした。それで飲料の世界を見てみると、ロングセラーがあったわけです。それが、ラムネであり、ソーダでした。他の業界に救われたんですよ。でも当時、一緒に出したのが、グレープフルーツ味でした。これと差別化するために、青い色をつけたんですね。今はソーダの青色はスタンダードになっていますが、実はガリガリ君が始まりだったんですよ。そして、しぐれをスプーンでかくとき、ガリガリと音がしますから、これがネーミングになった。ただ、私にはひとつ過去に苦い思い出があって、一般名称のネーミングを他社に真似られたことがあったんです。「ガリガリ」だけだと固有名詞にならない。商標登録ができないわけですね。そうしたら専務が、「じゃあ、”君”をつければいいんじゃないか」と。これが面白い、ということで後に口コミでも広がっていったんです。
菅:
ひょんなことで生まれるものですよね。「恋のから騒ぎ」は、5つくらいあった候補の中に「から騒ぎ」というタイトルが入っていて、それを見た当時の日本テレビの専務が「シェイクスピアだな、これがいいんじゃないか」と。でも、「そのままだとシェイクスピアのパクリになりますよ」と案を出した放送作家が言うので、「じゃあ、恋の、でもつけとけばいいんじゃないの?」と言ったらそのままタイトルになりました(笑)。ただ、面白かったのは、1回目の収録が、恋のから騒ぎそのものだったんです。若い女の子を説教する番組、というコンセプトをみんなが明確にわかっていました。一回目の収録がギクシャクすると、だいたい当たらないんです。でも、このときはミスも少ないし、撮り損ねもなかった。30分の番組で、50分もカメラを回していませんでしたので。
鈴木:
ネーミングのアイディアがポッと出てくる感じ、同じですね。
菅:
「恋のから騒ぎ」はテレビ欄にたくさん書けない、という事情もあったんですが、「踊る!さんま御殿!!」のときはゴールデンタイムですから、「明石家さんまさんの」というのを入れたかったんですね。でも、何かを前に付けたくて。そうしたら、「踊る」という言葉が突然どこかからわいてきたんです(笑)。
鈴木:
口が踊ってますからね(笑)。
菅:
それで「踊るさんま」ということで会議をやったんですが、まとまらない。僕は90分以上の会議はやらないんです。7時間も会議をやって、結論が出ていないのに、こんなに会議やったんだから、と安心しちゃうようなのが嫌いなんですね。一度切って、宿題にして持ち帰るんです。早く帰ればいいのにそのまま飲んだくれて、夜中に帰ってテレビをつけたら、白黒の時代劇をやっていて。「へぇ、昔の日本は面白いことやってたんだなぁ」と番組欄を見たら「歌う狸御殿」と書かれていたんです。これだ、と(笑)。タイトルも企画も、会議室で出たことなんてないですね。外に出かけたり、電車に乗ったり、突然、カラオケにみんなで行ってみるとか。音痴のヤツのほうが面白くて盛り上がって、みんな涙流して笑っている、なんてことになったりするんですが(笑)。どうでもいいバカ話をしているときに浮かんだりするんです。
鈴木:
私は会社が埼玉の田舎ですから、東京に出てくると刺激が大きくて、捨て目、捨て耳です。電車の中吊りに始まって、繁華街の看板をしげしげ眺めたり。英語やフランス語だけでなく、イタリア語やラテン語が増えているなと時代の流れを感じる。デパ地下に行けば、一番並んでいるところに並んでみます。やっぱり時代を肌感覚で感じたいんですよね。商品開発会議は7人ですが、一人ずつ必ず意見を言ってもらいます。ただ、選ぶ基準は、「こんなことをやりたい」と覚悟を決めているかどうかですね。本気でやりたいか。その企画に賭けているか。気持ちは伝わりますから。未来のことは誰にもわからない。だったら、失敗してでもやりたい、という人間に賭けます。「ガリガリ君」のコーンポタージュ味のときがそうでした。企画を出したのは2年目の社員です。会議で「これは絶対に売れます」と覚悟を決めて言っていた。夢を語って、目がキラキラ光っていた。だから決裁したんです。そうしたら、大ヒットになりました。
社長に認められたくて、この人のためになりたくて

鈴木:
私は、人の話を何しろ聞かない社員でした。生意気で。何を言われても、「yes ,but」ですから(笑)。学生時代が学生運動の時代。東大総長が式辞で鶏口牛後という言葉を使って、これを信じたんです。大きな組織のしっぽでなくて、小さな会社の頭になりたいと。私は小学校5年生のときに、当時、議員をしていた父を亡くしているんです。それまですり寄ってきていた人が、翌日から誰も来なくなった。父は借金をしていて、親戚も知らないふり。その時に世の中を知りましたね。赤城乳業に興味を持ったのは、かき氷1本でやっているヘンな会社だったことと、当時の会長に会ったとき、「この人は大物だ」と直感的に思ったことです。父親を早くに亡くしていることもあり、男親とはこういうものか、と何だか言葉にならない気持ちを感じたりもしました。もうひとつ、入社試験の感応検査で色んな香りを嗅いで当てるんですが、初めてやったのに全部当たってしまった。これは縁があるかも、と思いました。赤城乳業に感謝しているのは、本当に自由に仕事をやらせてもらったことです。商品開発だって、好きにやればいい、と。
菅:
僕は日本大学芸術学部の放送学科を出ていますが、放送学科卒というより、軽音学部卒という感じでした(笑)。バンドを組んで小さな事務所預かりのようになって。渋谷のライブハウスで毎週のように演奏して、週に2曲作って。一生懸命やっていたし、ポプコンでメダルももらいました。でも、サザンやツイストが出てきた時代。自分の才能のなさに気づくんです。それで、もしかしたらデビューできるかも、というときに辞めました。そこから、アメリカ人に嫁いでいた叔母のところに行って何カ月もぼんやり遊んで過ごして。オレはどうなるんだろう、という毎日でした(笑)。浪人して留年して26歳で、いい加減帰らないと、と帰国したら大学の先生に「兄が日本テレビにいる」と紹介されて。アルバイトで入ってADをしていたんです。生涯の恩人は「天才・たけしの元気が出るテレビ!!」を作ったことで知られる加藤光夫さんです。当時、携わっていた情報番組で、いきなり僕にディレクターを命じて。ADといっても弁当配りくらいしかしていないのに、いきなり生放送ですよ。びっくりしました。
鈴木:
急に生放送を任されるなんてすごいですね。
菅:
最初の生放送は平穏無事に済んだんです。周りは全員プロですから。意外に簡単だなんて思っていたら、2回目の放送直前5分前に梨元勝さんが特大スクープを持ってきて台本が全部、飛びまして。急な変更に頭の中、真っ白。スイッチャ―さんに「菅、うるさいから黙ってろ!」とまで言われてしまって。まったく使い物になりませんでした。これでディレクターはクビだろうな、アルバイトだし辞めようかなと思っていたら、加藤さんが、「楽しかったろ、テレビ面白いだろ、来週も頼むぞ」と。こんな人がいるテレビって、絶対に面白いと思ったんです。こういう人と一緒に仕事がしたい。この人に認められたい、と。その一心で仕事をしていました。後に呼ばれて頼まれたのが、渡辺徹さんと榊原郁恵さんの結婚式の総合演出です。各局、花形のエースディレクターが担当する仕事。でも、僕は社員でもないわけです。そうしたら「社員がやらないといけないなんて誰が決めた!やれるヤツがやればいいんだ!」と叱られて。翌年、僕は日本テレビに入るんです。でも、モノを作るのに、社員もへったくれもあるか、という加藤イズムは、僕のテレビ人生のベースになっています。
鈴木:
菅さんのことが大好きだったんですよ。だから、任せた。
菅: 加藤さんは東日本大震災の前日、亡くなりました。加藤さんの奥様から連絡をもらいましたが、僕は当時、編成の幹部で地震の影響もあり局内は大混乱でした。でも、上司に事情を説明すると、「会うなら今しかないだろう。今すぐ会いに行ってこい」と言ってもらったんです。僕は加藤さんから褒められたことは1度もないんですよ。いつもクソミソに叱られてばかりで。ワンカットワンカット、全部説明できるのか、とか。そんなのできるわけない(笑)。最後まで加藤さんが何を求めているのか、わからないままでした。でも、認めさせたかった。現場を離れてから、「お、いいんじゃない」なんて聞こえてくると本当にうれしかった。だから葬式の時に「加藤さん、生前に今みたいな優しい顔を見たかったな」って心の中でつぶやいてたんです。心のどこかでずっと加藤さんに認められたいというのがあったんでしょうね。
加藤さんは東日本大震災の前日、亡くなりました。加藤さんの奥様から連絡をもらいましたが、僕は当時、編成の幹部で地震の影響もあり局内は大混乱でした。でも、上司に事情を説明すると、「会うなら今しかないだろう。今すぐ会いに行ってこい」と言ってもらったんです。僕は加藤さんから褒められたことは1度もないんですよ。いつもクソミソに叱られてばかりで。ワンカットワンカット、全部説明できるのか、とか。そんなのできるわけない(笑)。最後まで加藤さんが何を求めているのか、わからないままでした。でも、認めさせたかった。現場を離れてから、「お、いいんじゃない」なんて聞こえてくると本当にうれしかった。だから葬式の時に「加藤さん、生前に今みたいな優しい顔を見たかったな」って心の中でつぶやいてたんです。心のどこかでずっと加藤さんに認められたいというのがあったんでしょうね。
でも、僕らはいくら自分で「これは面白い」と思っても、売れなければそれまでなんです。御託を並べて、こういうつもりで作ったのに伝わってない、と言い張る若いのもいますけど、僕は言っていました。「それなら日本中の視聴者にそれを言いに行ってこい」と。できないものは、言うもんじゃない。画面がすべてですから。言い訳なんて、意味がない。だから、自分が本当に面白いと思っていないものを人様に見せるほど失礼なことはない、と思っています。
鈴木:
同じですよ。私も入社のときに心酔した社長にいつか認められたいと思いながら仕事をしていました。この人だったらついていきたい、この人のために仕事してみたい、と思っていました。そういう思いは、強いですよね。そして、いろんなことを教えてもらった。一緒に金魚のフンみたいについていって、たくさんの人に会わせてもらって、人を見る目も養わせてもらった。個性的な人が多かったですね。そして会社は右肩上がりで伸びていって。そういうときって、失敗は隠されちゃうんです(笑)。
菅:
ヒットはたまたまですからね。ただ、どんな番組なの?と言われたとき、一言で言えるもの以外はヒットしないと思っています。ルールがたくさんあったら、視聴者はついていけない。「笑ってはいけない」にしても、ルールはひとつ。笑ったらひっぱたかれる。それだけです。「恋のから騒ぎ」は、キレイな女の子が頭をくしゃくしゃにされて説教される番組。スポーツだって、ルールがたくさんあったら、初めて見たとき「いいや、これ」になりますよね。持論は「テレビの前で正座している人はいない」なんです。どこから見ても単純でわかりやすくないといけない。
人がやっていないことばかりやってきた
菅: あとは時代ですよね。「恋のから騒ぎ」が始まったのは、若い女の子が「マンションを買ってもらった」「ダイヤの指輪なんてケチ」なんていうバブル後の時代だったんですね。その前に若い女子アナをたくさん集めて特番をやっていて、バブルな話を聞いた明石家さんまさんが、「今の若い子は説教せなあかんな」とポツリと言われていたんです。会社から「夜11時、お前とさんまさんで何かやれ」と言われたとき、思い出したのが「説教」だったんです。当時、さんまさんには各局から9本の番組オファーが来ていて、そのうち2つしかできないとされていました。企画書も何もない中で、「説教」の話をしたら「面白い、やろうか」ということになって。ひとつだけ言われたのは、「上品に作ってね」と。恋の話といっても、パッケージを上品にする。テレビって、下品な人は絶対にダメなんですよ。負のオーラを持っている人もダメ。さんまさんは、上品な人ですから。
あとは時代ですよね。「恋のから騒ぎ」が始まったのは、若い女の子が「マンションを買ってもらった」「ダイヤの指輪なんてケチ」なんていうバブル後の時代だったんですね。その前に若い女子アナをたくさん集めて特番をやっていて、バブルな話を聞いた明石家さんまさんが、「今の若い子は説教せなあかんな」とポツリと言われていたんです。会社から「夜11時、お前とさんまさんで何かやれ」と言われたとき、思い出したのが「説教」だったんです。当時、さんまさんには各局から9本の番組オファーが来ていて、そのうち2つしかできないとされていました。企画書も何もない中で、「説教」の話をしたら「面白い、やろうか」ということになって。ひとつだけ言われたのは、「上品に作ってね」と。恋の話といっても、パッケージを上品にする。テレビって、下品な人は絶対にダメなんですよ。負のオーラを持っている人もダメ。さんまさんは、上品な人ですから。
鈴木:
時代というのは大事なキーワードですね。「ガリガリ君」が出てきたタイミングというのは、食の習慣の転換期だったんです。それまでは、片手で外でモノを食べる、なんてことは行儀が良くない、という時代だったわけです。でも、子どもがそういうところからだんだん解放されていった。そういうときに出たんです。しかも、アイスは80ccが当たり前だとされていた時代に、125ccで出した。子どもが多くて、みんなホテっていて、クールダウンさせたかったから。でも出して10年ほどして、売れなくなった時期があるんです。それで、会社にお願いして予算をつけてもらって市場調査をしました。でも、データを見てもよくわからない。それで、大学の後輩にちょっと聞いてみたら、「調査なんて役に立ちませんよ。日本人ほど本音と建前が違う人たちはいませんから」と。
菅:
それはメチャメチャよくわかります(笑)。
鈴木:
それで、グループインタビューで直接、話を聞くことにしたんです。お客さんからは見えないよう、マジックミラーの向こうで待っていました。それで、真っ青になりました。当時のパッケージのキャラクターは、泥だらけの野球少年だったんですね。それに対して、辛辣な意見がどんどん出て。泥臭くて嫌い、あんなの誰が買うか、恥ずかしくてレジに持っていけない……。それでパッケージを変更したんです。ここから、売り場が「ガリガリ君」一色になっていくんですが、このとき、ひとつこだわったことがありました。パッケージを作ったのは、実は小さな調査会社の社員の人なんです。デザイナーでもなんでもないんですが、「自分にパッケージをやらせてほしい」と。私はその人にお願いしました。情熱があったからです。社内には3人のデザイナーがいましたが、彼ほどの情熱はなかった。実際、作ってもらいましたが、圧倒的な違いがあった。彼はこんなことを私に言ったんです。「この調査業界で、ガリガリ君を私以上に愛している人はいない」と。
菅:
素人に任せるなんて思い切ったことが、よくできましたね。

鈴木:
業界で生きていると、業界のことしかわからなくなるんです。そういうもんだよね、ということになる。そこからは、とんがったものは出て来ない。むしろ、まったく違う世界の人に頼んだほうがいいと思ったんです。リスクはありましたけどね。でも、さっきの菅さんの話と同じでしょ。私たちは、自分で対面販売できないんですよ。コントロールできない。でも、いい商品は商品自身がセルフエクスプレッション(自己表現)をしてくれるんです。それくらいパッケージというのは、大事なんです。このリニューアルで、ドーンと伸びるんですが、もっと伸びた時期がありました。それが、2010年、工場を公開したことです。食品業界が、自社工場を公開するのは珍しかった。たくさん取材を受けました。そうしたら、9000万本のプラスですよ。翌年、さらに9000万本。これも、オープンにするとか、安全とか、そうした時代の空気が大きかったんじゃないかと思います。結局、人がやっていないことばかりをやってきた会社なんです。それで、ドーンと伸びた。キャラクターのぬいぐるみを作ったときもそうでした。これが大ヒットするんですが、「ゆるキャラ」がその後、大きくブレイクするんです。失敗もたくさんしていますし、1000のうち970は失敗。ほとんど失敗。試作したアイスがあまりにもまずくて、当時の井上栄一社長に窓の外に投げ捨てられてしまったこともあります(笑)。何度も何度も失敗し、落ち込み、でもだからこそ、成功もあるんです。
菅:
テレビ業界がありがたいのは、当たらなかった番組は誰も覚えていないということです(笑)。「電波少年シリーズ」を作ったプロデューサーの土屋敏男という親友がいますが、彼とよく話をするんです。ラッキーだよな、失敗したら誰も覚えていないんだよな、と。彼なんて、オンエアの翌日に「番組を閉じるから」と言われたこともあるんです。でも、1年、2年のヒットなら誰でもできると僕らは思っているんです。5年続いて初めてヒットですよ。
若手の意見はちゃんと聞き、新しい感性を取り入れる
菅: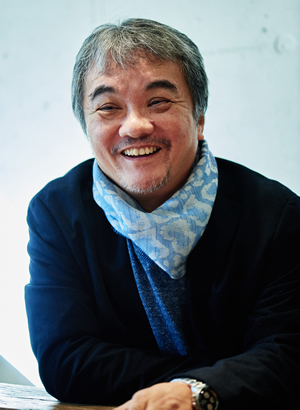 テレビ屋というのは面白くて、20%だ、大ヒットだ、なんて情報をオンエアの翌日の朝9時にもらって、「よっしゃ!」とガッツポーズをしたりするんですが、喜んでいるのは5分くらいなんです。「次どうしよう」というプレッシャーで、憂鬱になる。ヒットになったんだから、今日一日くらいバンザイして浮かれて酒でも飲んでいればいいのに(笑)。ある時、編成局長に呼ばれて、「3日後に2時間の特番を作れ」なんて命じられたことがありました。「えーっ!」と思いながらも、次の瞬間にはどうするか、考えてしまう(笑)。嫌な性分です。結局、好きなんだと思います。しかも、大きな勝負で指名をしてもらったら、それは男冥利に尽きる。よくぞ、選んでくれた、と。燃えるわけです。そして現場に降りていって、ヘイポー(斉藤敏豪)に話をしたら「えーっ!」とやっぱりなるわけですが、これまた「こういうのができるんじゃないですか」とすぐさま企画が飛んでくるんです。こいつも一緒なんだと思いましたね。もうみんな病気です(笑)。
テレビ屋というのは面白くて、20%だ、大ヒットだ、なんて情報をオンエアの翌日の朝9時にもらって、「よっしゃ!」とガッツポーズをしたりするんですが、喜んでいるのは5分くらいなんです。「次どうしよう」というプレッシャーで、憂鬱になる。ヒットになったんだから、今日一日くらいバンザイして浮かれて酒でも飲んでいればいいのに(笑)。ある時、編成局長に呼ばれて、「3日後に2時間の特番を作れ」なんて命じられたことがありました。「えーっ!」と思いながらも、次の瞬間にはどうするか、考えてしまう(笑)。嫌な性分です。結局、好きなんだと思います。しかも、大きな勝負で指名をしてもらったら、それは男冥利に尽きる。よくぞ、選んでくれた、と。燃えるわけです。そして現場に降りていって、ヘイポー(斉藤敏豪)に話をしたら「えーっ!」とやっぱりなるわけですが、これまた「こういうのができるんじゃないですか」とすぐさま企画が飛んでくるんです。こいつも一緒なんだと思いましたね。もうみんな病気です(笑)。
鈴木:
面白いですね。
菅:
「笑ってはいけない」は今年から僕は外れたんですが、「待ってました」と「マンネリ」との戦いで、同じ事をやっていては面白くないですから、若手に任せるようにしました。若い子にまかせると、こう来たか、というのがあって面白いですよね。一つだけ若手に言っていたのは、僕に向けてだけは作らないで、ということです。僕がわからなくても、面白ければいいんです。その意味で、独裁政権を作ってしまうと、番組はあっという間にダメになりますね。
鈴木:
ヒットのプレッシャーはありますよね。私はよく、わめいていました(笑)。トイレでわめいたり、風呂場でわめいたり。「バカヤロー」と大声で叫んだり。そうやって、すっきりしてから仕事を始める(笑)。血反吐をはいたけど、結局楽しいんですよ。
菅:
番組はチームで作りますが、大事にしているのはさっきの「加藤イズム」です。一番できて、一番みんなからの信頼がある人を総合演出にする。「えっ!オレがやるんですか!」なんて声が来ることもありますが、「誰が考えても、あなたでしょう」とはっきり言う。そしてチームをまとめていくには、スタッフそれぞれに役目をちゃんと明確に持ってもらう。それを会議で全員いる前で伝える。「仕切りがうまいから、ロケのチーフを頼む」といった具合です。なんとなくいる、というスタッフは作らない。ADが会議でしゃべらなかったら、「来週から来なくていいよ。ここは独演会じゃないから」と言います。鈴木さんの本には、僕の考えていたことがたくさん書かれているんですが、気を付けないといけないのは、モノをつくるとき、どんなに年が上でも、経験則を否定できないといけない、ということですよね。「そんなの、なんの意味があるんだ」なんて言いそうになるんですが、そもそも番組作るのに、意味なんてないんですよ。面白そうだから、やるだけなんです。

鈴木:
アイスも同じです。おいしそうだから、やるんです。
菅:
例えば新人のADの話もちゃんと聞く。あえて、話を揉んでみたりする。新人にしてみれば、有名な放送作家が自分の意見を揉んでくれたりするわけです。それから、「もう1回、考えてみようか」と返すと喜んで考えてくれますよ。でも「つまんない」とすぐに戻してしまったら、二度と発言しないと思います。テレビには10年早い、はないですが、10年遅い、はある。実は入って来たばかりの人間こそ、一番視聴者に近いんです。だから、その人の意見は正しい。実は、そのことを忘れちゃうのが、一番怖いところなんです。
鈴木:
おっしゃる通りですね。最近は、商品を出すサイクルがどんどん早くなっています。目標決めて、一定期間の中でやらないといけない。もたもたしていると、置いて行かれてしまう。でも、消費者に一番近いのは、若い人ですから。中にいると、仕組みばかりに慣れていってしまう。判断を出す基準が、社内の仕組みからできてしまったりする。これはダメですよね。若い人の意見を聞かないと。新しい感性をつかまないと。その意味では、むしろ会社のことを知らないほうがいい。そのほうが新鮮になるから。
最後は「気持ち」を大事にする
鈴木:
意見が出やすい環境を作るには女子会みたいな雰囲気がいい。そのために赤城乳業でやってきたのが、管理職が入らない会議です。あるいは、社内コミュニティ。いろんな仕事をするジョブローテーションもいいですね。開発会議は、ミニ商品開発会議がいいです。大勢集まる会議の前に、3人くらいでミニ会議をやる。あとは、社外の人に加わってもらうことですね。容器メーカー、素材メーカーなど。社内だけだとどうしても発想が狭くなる。外から人を入れたほうがいいんです。そのためにも、いい関係を築いておかないと。
菅:
僕もまったく違う世界の友人たちとよく飲みます。検察官とか医師とか市会議員とか(笑)。テレビ局にたくさん置いてある週刊誌や雑誌も見ない。だって、雑誌に出た時点でもう情報は古いんですよ。テレビの人間だったらその先を行って流行を作り出さなきゃ。だから車の本かゴルフの本しか読まない。なぜって僕が好きだからです(笑)。これはどの仕事にも共通する事だと思うのですが、人間関係も非常に大切です。大事なことは絶対にウソをつかないことですよね。明石家さんまさんもそうですが、すごい人たちというのは、自分に都合のいいウソは瞬時に見抜きますから。逆に一番弱いのは、純粋さです。本気でぶつかっていけば、それは伝わる。本気じゃないとダメ。信頼も一瞬で崩れます。
鈴木:
人としてどうか、ということは大事なことですよね。基本的な事ですが、時間を守る、約束を守る。僕は講演も必ず早く行きます(笑)。あと、相手の欲もちゃんと見ることですよね。相手もお金儲けしたい。そうでないと、誰もついていきません。商売をするなら欲は道連れでないと。だから、営業に来る人にはレポートが書けるように、ちゃんと情報を出してあげないといけない。相手に気遣いできないと、人が来なくなりますね。あの人のところに行ってみよう、会いたい、と思ってもらえる人になる。そういう人のほうが、情報も集まってくるし、楽しい人生が送れると思います(笑)。
菅:
「おみやげ」、大事ですよね。例えば僕たちは番組出演者のブッキング権限を持っているわけです。誰を使うか。使える人は限られますから、すいませんと謝ることの方が多いのですが、逆にOKのときは大事にその情報を使う。ときどき事務所の社長がお見えになることがわかっていたときがそうです。そういうときは、挨拶が終わって社長が帰られたあと、すぐにマネジャーに電話をするんです。そうすることで、「さすがは社長」ということになるじゃないですか。社長が挨拶に行ったら一発で出演のOKをもらえたって。社長のメンツを立ててあげるんです。せっかくのブッキングですから、最大限に情報は使います。
鈴木:
それは上手。社長はうれしいでしょう。やっぱり気持ちですね。
菅:
そうですよね。企画も同じ。最後は、これを命賭けてやってみたい、と思えるか、だと思うんです。気持ちが大事。その点で、テレビに関して今は憂えているんですけどね。もっとサムライであってほしい。企画は、人の真似をした段階でダメなんですよ。自分のオリジナルで逆に人から真似されるようなものを作らなきゃ。
鈴木:
私も人の考えの逆を行く、「YES,BUT」の精神でやってきました。歴史から学んでも良いけど、人の真似をしない。何事も二番煎じはダメなんですよ。
菅:
番組もどこかで似たようなもの見たな、というのはすぐ終わってしまいます(笑)。
鈴木:
大事なことは、信念を持つことだと思っています。Going my way信じた我が道を突き進む。時代は流れているんです。いずれ、自分の道と時代がピタっと合わさるときがくる。そのときを逃さないこと。それを信じることだと思います。講演でもお伝えしているのですが、失敗をたくさんするからその先に成功があります。失敗を恐れずどんどんチャレンジすることが大事なんだと皆さんに伝えたいですね。
おまけ★今までにお二人がこれはすごい!負けた!と思ったものはありますか?
鈴木:
ロッテのドラキュラアイス「クロキュラー」です。真っ黒のアイスで食べると口の中が紫になるんですよ。この発想はなかったですね。本当にビックリしました。
菅:
テレビ東京の「大食い王決定戦」や「池の水ぜんぶ抜く」シリーズです。ギャル曽根ちゃんのような新しいキャラクターの子が出てきたり、予算をかけずにここまでヒットになる番組はすごいですよ。

――企画:土橋 昇平・一瀬裕司/取材・文:上阪徹/写真:三宅詩朗/編集:鈴木ちづる


鈴木政次()
1946年 茨城県出身。1970年 東京農業大学農学部農芸化学科 卒業後、赤城乳業株式会社に入社。1年目から商品開発部に配属される。愛すべき失敗作を生み出しながらも、「ガリガリ君」、「ガツンとみかん」…


菅賢治()
1954年、長崎県生まれ。1980年、日本大学芸術学部放送学科卒業後、アメリカ放浪の旅に出る。帰国後、日本テレビエンタープライズに契約社員として入社。渡辺徹と榊原郁恵の結婚式の総合演出を担当し、視聴率…