歴史の中から現代に通じる実学を選び出し、執筆して世に送り出すという新境地を開拓した童門冬二さん。歴史に見る組織と人間という童門さんのテーマの背景には、30年以上に及ぶ東京都職員としての公務員生活と、行政の現場でさまざまな現実に立ち会ってきた体験があります。
都庁在職中の1960年に小説『暗い川が手を叩く』が芥川賞最終候補に。そして1979年の退職後からは作家活動に専念され、数多くの書籍を上梓。多くのベストセラーも輩出されました。大変エネルギッシュで、80歳を過ぎた今なお、月に500枚を超える旺盛な執筆を続けられています。
名講演者としても知られ、現代における人、教育、組織、経済、社会、文化のあり方を、歴史という人間ドラマを題材に語られる話しぶりには、数多くのファンがいます。 今回は、変革の今、求められるリーダーシップについて、お話をお聞きしてきました。
まずは自分を確立する。足りないところを歴史で補強する。
―――企業の経営者やリーダーが、舵取りの難しい時代です。今こそ歴史に学ぶべき、なのでしょうか?
「『歴史に学べ』、とよく言われますが、ただ歴史に学ぶというのは、実は間違いなんです。まず必要なのは、経営者やリーダーが今、自分たちがやっていることは正しいんだと、自分を是認することなんですね。基本的に歴史に対する姿勢というのは、自分の考え方があって、それを補うために、あるいはそれをより輝かせるために、助長材として取り入れていくのがいいんです。まるごと何もない、がらんどうな状態の人が、100まるまる全部取り入れるのはいただけない。まず自分というものが7、8割あって、2、3割の欠落している部分を補強する。自分が主で、歴史は従という考え方をしたほうがいい。多くのビジネスマンはそれを認識されていない印象がある。まずはしっかり自分を持ち、そのことに自信を持つこと。その上で講演を聞いたり、本を読んだりして、足りないところを歴史を学ぶことで補えばいいんです。
歴史上の人物もパーフェクトではありません。一人の人間から丸ごとは学べない。例えば、人間の衣食住の暮らしの中に、新しいカルチャーを取り入れたことから先進性を学ぶなら、織田信長。家臣へその仕事の目的を明確に提示し、チームワークをよくして、部下が気持ちよく仕事をするように仕向けていったことからマネジメントを学ぶなら、豊臣秀吉。そんなふうに自分に都合のいいところ、自分が発見できたところを盗めばいいんです 」
―――今の経営の現場では、「これまでのやり方が通用しない、組織パフォーマンスを高めるために、どうすればいいかわからなくなってしまった」、という経営者の声も聞こえてきます。こういうことも歴史に学べるのでしょうか?
「例えば、豊臣秀吉という人物は、それまでのやり方ではうまくいかなかったことを、次々に成功させているんですね。有名なものに織田信長の家来時代の塀修理がある。信長に命じられ、工事奉行が100人の労務者を使って塀の修理に挑むけれどうまくいかなかった。それを、秀吉が引き取るんです。どうしてうまくいかなかったのかといえば、『何のためにそれをやるのか』、工事を担う労務者がつかんでいなかったからでした。現場の100人が全員、目的を喪失していた。秀吉は工事箇所を自分の目で見て、まずは10カ所に分けるんです。そして100人を10人ずつの10組にしようとした。でも、誰と誰がどの組に入るかは、自分たちで決めろ、と言ったんですね。好き嫌いもあるだろう、決めたら集まれと。そしてどの場所を担当するかはクジで決めて、最初にできた組には信長から褒美を与える、とした。ただ仕事を与えるだけではダメなんです。まずは自分で現場を知り、その上で部下に考えさせなくちゃいけない。部下にやる気が出るような工夫を意識しないといけないんです。
これからの組織論としては、タスクフォース的なものがいいと私は思います。歴史もそれをたくさん語っている。例えば、織田信長は合戦のたびごとに編成を変えていました。美濃攻めのとき、叩き上げの豊臣秀吉を使ったのは、彼が最も適任だったからです。あの輪中の地域への大変な城攻めは、ぬるま湯で育った織田家の家来では無理だと考えたんですね。そしてこのとき秀吉は、拠点として墨俣一夜城を、家来ではなく木曽川沿いの土木建設業者たちに作らせたのです。輪中地帯である川の流域に堤を築く専門技術を持った連中に任せ、完成できたら家来にするという見返りをつけた。これが成功を呼び込んだ。ある目的を立てたとき、そのたびごとに最適な特別チームを作る。目的が完成したら、解散して元に戻る。編成と解体を自在にしていく。やわらかい組織に変えていかないと、硬直化してしまいます。あんまりパーマネントにこだわると、サビがわいてくるんです。こういうことも歴史に学べると思いますね」
――――最近では、若い社員がすぐに不平不満をこぼす、辞めてしまう、と困っている会社も多いようです。
 「やりたいことをやらせてくれない、最初に考えていたことと違った、やらされている仕事が嫌だ…。でも、それはちょっと気が短すぎます。それで辞められてしまうのは、上の責任と言わざるを得ない。上司と部下でよく話し合わないといけないですね。でも、そういう仕事の不平不満の話は、会社ではあまりできない。焼き鳥屋に行ってお酒を飲まないとね(笑)。いずれにしても上の努力が必要です。
「やりたいことをやらせてくれない、最初に考えていたことと違った、やらされている仕事が嫌だ…。でも、それはちょっと気が短すぎます。それで辞められてしまうのは、上の責任と言わざるを得ない。上司と部下でよく話し合わないといけないですね。でも、そういう仕事の不平不満の話は、会社ではあまりできない。焼き鳥屋に行ってお酒を飲まないとね(笑)。いずれにしても上の努力が必要です。
江戸時代に、農村復興政策を指導した二宮金次郎は、農民にむけて、『鍬をふるって土を耕すということは、(農民が持っている)土に対する愛情を、鍬を通じて伝えることだ』、と言っていました。土はモノ言わない。でも、実は土はわかっているんだと。だから、農民が土を愛せば、蒔いた種を土は立派な農作物にして返してくれる。その徳に対して報いないといけないという報徳の精神をもって恩を返すわけです。でも、これは普通の土の話。土には荒れ地があります。耕しても、時間と労力の無駄だと見捨てられる土がある。でも、見捨てたらダメだと金次郎は言うわけです。荒れ地も徳を持って掘り続けないといけない。荒れ地なるがゆえに、相当深いところまで、巡り会うまで掘り続けないといけない。そうすると、農民は大きな徳に出会える。見当違いのところに損得があったりする。問題児と言われる社員も、上が見放しちゃダメなんですよ。根気よく、相手のいいものが見つかるまで掘り続けないといけない。それが、大きな徳を生む可能性を秘めているんです」
リーダーの意識と行動で、組織は変わる
――――「不透明な時代、しかも不況で、なかなか成功体験が得られない。だから、組織が疲弊している」、という声も聞こえてきます。
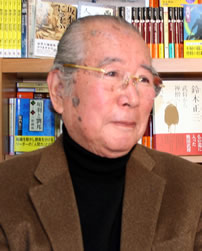 「2点間の最短距離は直線である、という評価方式を変えなきゃダメでしょうね。武田信玄にしても、毛利元就にしても、織田信長にしても、成功率は70%に抑えていました。もちろん100%を目指すのはいい。でも、成功の度合いは70%くらいだと思っていたほうがいい、ということです。これを100%に置いてしまうというのはトップの思い上がりです。これでは、会社の方向を誤りかねない。失敗の度合いが20~30%くらいあったほうが、次への継続という意味でもいいんです。永遠性のある組織運営にもつながる。
「2点間の最短距離は直線である、という評価方式を変えなきゃダメでしょうね。武田信玄にしても、毛利元就にしても、織田信長にしても、成功率は70%に抑えていました。もちろん100%を目指すのはいい。でも、成功の度合いは70%くらいだと思っていたほうがいい、ということです。これを100%に置いてしまうというのはトップの思い上がりです。これでは、会社の方向を誤りかねない。失敗の度合いが20~30%くらいあったほうが、次への継続という意味でもいいんです。永遠性のある組織運営にもつながる。
もうひとつ、これは徳川家康の哲学ですが、人間がすべてパーフェクトだなんて思うのは、間違いだ、ということです。みんな、いいときもあるが、悪いときもある。想像の70~80%だと思え、と。一方で家康は、足りないと思った部分はグループで補いました。だから、家康の組織論では、江戸幕府を開いてから、幹部のポストは単数はないんです。必ず複数。大老も老中もそう。1人ではない。町奉行は、2人の1カ月ずつの交代制だった。こうなると、部下もまわりの人間も比較ができる。あの人のここはいい、前のほうが良かった、あの人はここが足りない、と。これで緊張感も生まれる。複数制は、それこそ今の日本の組織でも大いに参考にできると思います 」
――――マネジメントに悩んでいる経営者やリーダーも多いようです。部下がなかなかやる気になってくれない。上の言うことをなかなか聞いてくれない、と。
「経営者やリーダーは、『感動』というものをもっと掘り起こさないといけないのではないでしょうか。豊臣秀吉の家臣だった頃の徳川家康に、こんなエピソードがあります。秀吉が、茶の湯に凝ってたくさん集めた高価な茶道具を家康に自慢した。『徳川殿はどのような道具をお持ちかな。内大臣という役職に就かれたのだから、さぞかし見事なものをお持ちだろう』、という問いに家康はこう答えるんです。『取り立てて、財宝と呼ぶような道具は持っていません。敢えてお答えするなら、私の財宝は、私のために命を預けてくれる500人の部下です』、と。秀吉にすれば、『よく言うよ、この狸が』、と思ったかもしれない。部下として、かわいくない発言なんですよ。それこそ、天下人となった豊臣秀吉は誰も逆らえない存在であり、もしかすると、戦国の世ですから、秀吉の機嫌次第では、その場で家康は斬られるかもしれなかった。でも、それを承知しながら、家康は自分の思うところを実直に発言した。これは一つの例ですが、リーダーは命がけで物事に当たることが大切です。部下のためなら斬られる覚悟もある、と。だからこそ、部下は感動するわけですね。これを芝居のごとくパフォーマンスでやっても、ヤラセだと見抜かれてしまう。また言ってやがる、ということになりかねない。心の底からそう思い、自分のすべてを賭ける。そんな一言一言でなければ迫力は出ないんです。今の時代も、問われているのは、リーダーとしての覚悟から生まれる言動なんです。
また、リーダーは、まわりをキョロキョロ伺わないこと。今は、誰もがまわりの評価を気にする時代になってしまっている。みんなビクビクし過ぎています。だからこそ、『オレは間違っていない、やるべきことをやるんだ』、とまわりの評価に左右されない自分の本心からの行動をしてほしいんです。幕末のリーダーの一人、勝海舟はこう言っていました。『やるのはオレ。評価は他人。オレの知ったこっちゃない。そんなもの、放っときゃいいんだ』、と 」
――――部下にすれば、経費節減ばかりで面白くない。どうしていいのかわからない、という思いもあるようです。
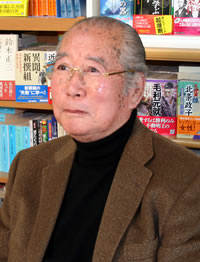 「現状をモノサシにして考えるから、次々に削られている、なんて思えてしまうんですよ。じゃあ、削られたものが本当に必要だったのかどうか、考えてみないと。最初から本当はいらなかったんじゃないか。知恵を働かせればかわりになるものがあるかもしれない。出し惜しみせずに自分の能力を出せば、やれてしまうかもしれない。現状をひとつのモノサシにして評価するのが、そもそも間違いなんです。一方で経営トップもコピー用紙1枚を倹約して本当に赤字補填になるのか、考えてみるべきです。そんなものは微々たるもの。もっと違うことができるのではないか。重役が自らボーナスを削るとかね。
「現状をモノサシにして考えるから、次々に削られている、なんて思えてしまうんですよ。じゃあ、削られたものが本当に必要だったのかどうか、考えてみないと。最初から本当はいらなかったんじゃないか。知恵を働かせればかわりになるものがあるかもしれない。出し惜しみせずに自分の能力を出せば、やれてしまうかもしれない。現状をひとつのモノサシにして評価するのが、そもそも間違いなんです。一方で経営トップもコピー用紙1枚を倹約して本当に赤字補填になるのか、考えてみるべきです。そんなものは微々たるもの。もっと違うことができるのではないか。重役が自らボーナスを削るとかね。
関ヶ原の合戦で負けた上杉家は、会津120万石が米沢30万石に減らされてしまった。ところが、『家来6,000人を一人もリストラしてはならない』、と上杉景勝を支えた智将、直江兼続は言いました。しかし、石高が4分の1になってしまったわけですから、減給するしかない。全員平等に4分の1に減らすのは簡単です。しかし、例えば200万円をもらっている重役は4分の1になっても50万円残る。ところが、20万円の平社員は4分の1になると5万円になってしまう。これでは食えるわけがない。そこで上役ほど減給率を高めたわけです。家来も3分の1にしたけれど、自分自身は12分の1にしてしまった。こうなれば、下は意気に感ずるわけです。そういう大胆な発想をリーダーは持たないといけない」
「誰かさんのために」という思いを組織全体で持てるか
―――今の状況というのは、歴史に例えると、どんな時代に当たるのでしょうか?
 「ひとつはやはり『戦国時代』でしょうね。これまでの日本式経営の根幹にあったルールやマニュアル、日本的な信条主義が棚上げになってしまった。能力主義や実績主義になり、数字が力を持つようになった。下が上を超える、下が上に勝つような下剋上の風潮ができてしまっている。もうひとつは、『幕末開国時代』でしょう。この時代は、時代が大きく変わったという意味では、『第二の戦国時代』といってもいい。第一の戦国時代では、武器や勇気がモノを言いました。誰が戦争に強いか、という合戦によって結果が出たわけで、学問などいらなかった。ところが、第二の戦国時代は、言論の自由が広まり、思想、考え方、表現力、言葉が必要になった時代です。今という時代は、これら2つの時代に、『IT』を加えたものだと思います。ITの登場は、21世紀特有の現象でかつての日本の歴史にはなかったことを引き起こしています。結果的に、第一の戦国時代と幕末開国時代にITが加わった3つの要素が複合した時代になっている。
「ひとつはやはり『戦国時代』でしょうね。これまでの日本式経営の根幹にあったルールやマニュアル、日本的な信条主義が棚上げになってしまった。能力主義や実績主義になり、数字が力を持つようになった。下が上を超える、下が上に勝つような下剋上の風潮ができてしまっている。もうひとつは、『幕末開国時代』でしょう。この時代は、時代が大きく変わったという意味では、『第二の戦国時代』といってもいい。第一の戦国時代では、武器や勇気がモノを言いました。誰が戦争に強いか、という合戦によって結果が出たわけで、学問などいらなかった。ところが、第二の戦国時代は、言論の自由が広まり、思想、考え方、表現力、言葉が必要になった時代です。今という時代は、これら2つの時代に、『IT』を加えたものだと思います。ITの登場は、21世紀特有の現象でかつての日本の歴史にはなかったことを引き起こしています。結果的に、第一の戦国時代と幕末開国時代にITが加わった3つの要素が複合した時代になっている。
ITの登場で何が出てきたのかといえば、子どもから大人まで、うるさい人間が増えてしまったということです。注文が多くなった。簡単にたくさんの情報が入るようになり、自分が生きていく上で必要なモノやサービスを選ぶモノサシを、ITで得てしまったわけです。だから、みんな一家言を持つようになった。それに応えなきゃいけない。企業は、選ばれるということを承知の上で、モノやサービスを作っていかないといけない。それには、こういう品物なら××、という顧客との信頼関係が必要でしょう。『~なら』という『らしさ』です。そしてこれは、無機物が作るのではなく、人間が作るんですね。したがって、作っている人間も『~なら』と言われて選ばれる『らしさ』を持たないといけない。個人も、この仕事ならキミに任せられるという力が求められる。企業も個人も、××さんの言うことなら今回はお世話になろうと言わせるだけのものを作らないといけないということです」
―――では、こんな時代のリーダーには、どんな要素が求められてくるのでしょうか?
「大分県知事だった平松守彦さんが、かつて『グローカリズム』という考え方を提唱されていて、私は強く賛同しました。彼は一品一村運動を行い、姫島のエビや椎茸などをブランド化した人です。農作物でも、グローカリズムを持って作らないといけない、と。これは3つの言葉からなる造語なんですね。まずは『グローバル』、国際感覚を忘れない。次が『ナショナル』、国内問題に関心を持つ。その上で『ローカル』、大分県を意識する。大分の片隅で仕事をするにしても、国内・国際関係を欠いたら生きていけないということです。平松さんは物事の本質を早くから突いていました。
このグローカリズムを分解すれば、これからのリーダーには何が必要なのか、具体的な要素が出せます。先を見る力『先見力』、その元になる『情報力』、それを分析する『判断力』、多くなる選択肢からチョイスする『決断力』、決めたことを実行する『実行力』、そしていずれも人間の生身の行為だから健康でなくてはならないから『体力』。これが、グローカリズムを分解すると見えてくるリーダーの条件だと私は思っているんです。そしてここに、『~なら』と言わせる『らしさ』を加える。 でも、このすべてを完璧に持っていることは難しいでしょう。実際、歴史上の人物でもそうだった。武田信玄、上杉謙信なら『体力』が欠けていた。信玄は51歳で肺病で死んでしまうし、謙信は酒の飲み過ぎで血管が切れて49歳で死んでしまう。ところが、信玄も謙信も、武田軍団、上杉軍団と呼ばれる結束を誇るわけですね。親方のためなら討ち死にしてもいいというやつばかりがいた。『~なら』と許せる「らしさ」が、健康を欠いてもあまりにあるほどの状態を作ったということです。組織全体がトップリーダーのオーラによって、モラルややる気に満ちてしまったわけです」
 ―――やはりリーダーによって、組織は大きく変わる、ということですね?
―――やはりリーダーによって、組織は大きく変わる、ということですね?
「一番大事なのは、何のために仕事をしているか、です。誰かさんのために、という思いを持てるか。それを組織に持たせることができるか。会社には、創業者が会社を始めたときの理念が必ずあるはずなんです。何のために会社を興し、事業を始めたか。これを上の人間が忘れずに、常に社歴の浅い若い人に植え付けていくことです。部下は、何のためにやっているのかという方向性がなければ、何をやっていいか、わからなくなっていく。さらに、自分が何に貢献しているのか見えずに、自分の存在意義が確認できなくなる、これでは辛いですよね。自分の仕事で誰かが喜んでくれている。リーダーは、それを部下にしっかり認識させることです。
私が講演をするのも、本を書くのも、誰かさんに喜んでもらいたいから。その一言に尽きます。それだけなんです。講演を聴く、あるいは本を読む方の全員とは言わない。何人かの方が、私の話を会社に持ち帰り、それをみんなで共有してもらえたならば、こんなにうれしいことはない。パテントなんかありませんから、どんどん話をして下さっていい。童門が言っていた、なんて言わずに自分のものとして話せばいい。大事なことは、その話が生きていくことですから。たくさんの、人の役に立つこと、ですから」
――本日はお忙しい中、貴重なお時間をいただきまして、ありがとうございました。
取材・文:上阪 徹 /編集・写真:田中 周子
(2009年12月 株式会社ペルソン 無断転載禁止)


童門冬二どうもんふゆじ
作家
― 恕<じょ> ― のきもちを大切に... <スタッフからのメッセージ> かつて東京都に勤め、都立大学事務長、広報室課長、企画関係部長、知事秘書、広報室長、企画調整局長、政策室長という重職を歴…
スペシャルインタビュー|人気記事 TOP5

Vol.50 子宮頸ガン・更年期障害を乗り越えて ~デビュー40周年の今思…
森昌子

Vol.01 三流の一流~キートン山田~
キートン山田

Vol.27 癌を乗り越えて 今を生きる
関口照生

Vol.85 どうせやるなら、熱くやったほうがいい
松田宣浩

Vol.73 お笑いブームで売れっ子たちが外車を買っている中、僕は音楽に全…
古坂大魔王
講演・セミナーの
ご相談は無料です。
業界21年、実績3万件の中で蓄積してきた
講演会のノウハウを丁寧にご案内いたします。
趣旨・目的、聴講対象者、希望講師や
講師のイメージなど、
お決まりの範囲で構いませんので、
お気軽にご連絡ください。






